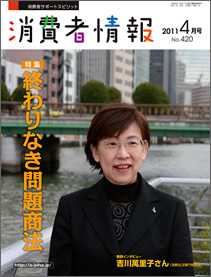リスクコミュニケーションの考え方は、食品の安全・安心が社会問題となった頃に注目されました。
厚生労働省では、新しい政策をする場合に必ずリスコミ(リスクコミュニケーションのこと)を全国各地で開催するようになり、ホームページでも告知され、一般の消費者も参加できます。今では、農林水産省など他の省庁でも実施されています。
厚生労働省のホームページに詳しく解説されています。
簡単にいうと、絶対安全というものは存在しない。必ず危害(リスク)が存在する。そのリスクが、どの程度だったら受け入れることができるのか、ということです。
日本人は、安全か、安全でないか、いわゆる、「0」か「100」かという考え方を根強く持っています。
したがって、農薬が少し基準を上回っただけで生命に危害が及ぶと過剰反応したりします。
科学的にあらわされるのは「安全」であり、「安心」は気持ちの問題です。
「安全」は固定されているのですが、「安心」は人それぞれであるのです。
しかし、「安全」と「安心」を混同してしまっています。
そこで、国や事業者や消費者などの利害関係者が話し合うことによって、「安全」と「安心」をお互いに共有する場をもとうというのが「リスクコミュニケーション」です。
残念ながら、日本では十分に浸透していません。
今、まさに、地震で津波や原発など、日本人にリスクコミュニケーションが試されているのです。
今回の地震の規模と一連の災害を想定すべきものと考えるのか、想定を超えた想定外のこととして考えるのかで大きな違いがあります。
想定すべきものとしたら、それに見合う金銭的・精神的な負担をしてきたのか。
想定外であれば、それを受け止め前向きにがんばる。
批判する根拠(権利)と今までの行動(義務)との整合性があっているにか。
消費者は正しく受け止めることができるでしょうか。
たとえば
①20mを超える津波に耐えうる防波堤をつくることが必要か?
→多額の費用をかけて100年に一度の備えをするのか、大増税になっても国民はその費用を負担する覚悟があるのか
②原発は危険だからやめるべきか?
→そうなれば計画停電が毎日数時間実施されるような電力不足に対して、電気を使わない暮らし、新エネルギーへの転換の費用負担、高額な電気料金が必要な現実をどう受け止めるのか
③低レベルに汚染された水を緊急に海に流すことと、流さずに高レベルの水でもっと汚染され事態が悪化するかもしれないことのどちらを選ぶのか
④汚染地域の食品や水を消費者が避けるのか
⑤ガソリン車の脱却をはかるのか
などなど
これらは、国に強制されるものではなく、国民が選択するものです。
税金を払っているのは国民であり、享受を受けているのも国民です。国は国民で成り立っています。
私たちが選択するのです。権利と義務のようなものです。
今まさに、真剣に、一人一人が今後の日本のことを考えなければなりません。
政治に無関心な国民は、もっともっと政治に関心を持たなければなりません。
日本の国民、消費者の意識が変わることを期待しています。
長々と書きましたが、実は私が言いたいのは、相談現場も、まさしく「リスクコミュニケーション」の世界なのです。
消費者が100%勝つ、事業者が100%勝つ、というのもあるでしょうけど、基本的には、どこかで折り合いをつけなければなりません。その過程が、「あっせん」なのです。
事業者が100%悪いからといって、すべてそのとおり進むとは限らないのです。
相談員として正義を貫き100%を求めるは基本のスタート位置ではありますが、現実にあわせて、折り合いをつけることが重要です。
まさしく、コミュニケーションです。
どのタイミングで。
どの程度の割合で。
一方的なものはコミュニケーションではありません。
日本人はコミュニケーションが苦手です。
しかし、相談員はしっかりコミュニケーションしなければなりません。
相談員に十分なコミュニケーション能力が備わっているのでしょうか。
知識習得にかたよっているスキルアップではなかなか難しいのではないでしょうか。
私は、このコミュニケーションについて、みなさんに考えてもらいたいのです。
今後、コミュニケーション能力を身につけるヒントやポイントをこの講座で示すことができたらと思います。
(平成23年4月5日 初稿)
Copyright c 2011- 消費生活相談員スキルアップ講座 窶錀 All Rights Reserved