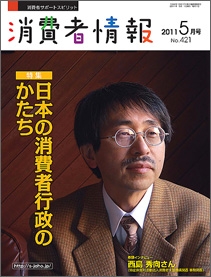ネットの知識 「クラウド」
前回、パソコンの知識として「データーの復旧」について説明しました。
今回の震災の後に、データー保管の重要さについて、データーは「クラウド」にあるから大丈夫だ、とか、これからは「クラウド」でデーターを管理しよう、という話が出てきているのはご存知でしょうか。
2年ほど前から「クラウド」という言葉が聞かれるようになりましたが、具体的にイメージすることが難しく、何のことか分からない方もおられると思います。何かのきっかけに、ある言葉や専門用語が一気に知られることになりますが、今回がそうかもしれません。
「クラウド」とは、クラウドコンピューティングを略した言葉で、データを自分のパソコンではなく、インターネット上に保存する使い方やサービスのこと、と説明されています。
「クラウド」は「cloud」、「雲」です。データが自分の手元ではなく、空にある雲にあるとイメージします。雲は、どこにいても見上げることができますよね。つまり、データーが手元にあるのではなく、雲にあり、どこからでも見ることができるということです。
では、具体的な事例を言いますと、この講座の実践編でも紹介したことのある「フリーメール」がその典型例です。グーグルのGmailであれば、メールを確認するのに、ネットに接続して、IDとパスワードを入れれば、どのパソコンでも見ることができますよね。当然ながらデーターはネット上に保存されているので紛失する心配はありません。
「サンダーバード」というメールソフトで自分のパソコンにダウンロードするという実践の話もしましたが、データーをネット上から削除せず保存したままにするという設定であれば、自分のパソコンが壊れたとしても、メールソフトから読み込めなくなったとしても、ネットから確認できますし、必要なら、もう一度、メールソフトで設定しなおせばいいのです。
以前は、ウェブメール(フリーメール)でも容量制限があり、削除しなければメールボックスが一杯になったのですが、今はGmailでは7Gの容量があり、文字メールだけであれば、ほぼ無限といってもいいでしょう。
Gmail以外のウェブメール(フリーメール)も無料で使える容量を競い合ってますので、容量不足を気にする必要がなくなりました。
また、ホームページもそうです。
以前はホームページビルダーなどの専用ソフトを使って自分のパソコンで作成したデーターをアップさせていましたので、自分のパソコンにトラブルがあるとデーターが失われてしまいます。
今のブログはウェブメールと同じように、ネット上でIDとパスワードを入れて使用するので、データーはネット上(クラウド)に保管されています。
私のこのブログもレンタルサーバーを借りてウェブ上に保管しています。
企業のデーターの持ち出しというセキュリティの問題も取り上げられています。最近では、会社のパソコンからフロッピーディスクやメモリーカードへのデーターの書き込みをできないような設定にしていますし、ハードディスク自体をパソコンからなくして、企業内のサーバーからデーターの読み書きをしているところもあります。これも小規模のクラウドのようなものですが、これを自社ではなく、信頼できる管理会社と契約して安全なネット上で管理するという動きもあり、これが冒頭に紹介したものです。
個人ではネット上のデーターの保管先として、「DropBox」などの無料のスペースもあれば、レンタルサーバーなどの有料のスペースまで多種多様です。
もちろん、クラウドとはいえ、最終的には地上にあるデーターセンターのハードディスクに保管されるわけですから、そこが壊滅したら終わりです。しかし、サーバー会社の威信をかけて安全対策をしているところです。
「クラウド」のイメージが具体化してきましたでしょうか。
そろそろ、この言葉は知っておくべき言葉になりつつありますので、相談員として一般消費者が認知する前にぜひとも知っておきましょう。
ちなみに、「ブログ」という言葉も、最初は「WebをLogする」という意味で「Weblog(ウェブログ)」と言われていました。7年ほど前でしょうか。私はまだホームページビルダーを使用していました。「Weblog(ウェブログ)」が略されてBlog(ブログ)と呼ばれるようになり、今では誰もが知っている言葉になりました。