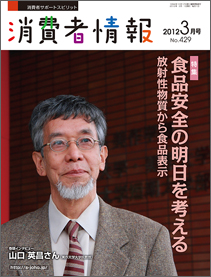あなたの常識は本当に常識?
消費者センターは中立な立場でスタンダードを示すことが仕事であると考えています。
しかし、そのスタンダードが難しいのですね。
また、そのスタンダードこそ「常識」ともいえるものです。
基本的には、このスタンダードは変わらないものです。
しかし、人によって、このスタンダードが変わってきます。
「そんなこと常識だ」と私たちは思うことがあります。
しかし、その常識は本当に常識でしょうか?
あなたの思い込みになっていませんか。
これはバイアスについて解説した記事にも共通しています(バイアスを持たないようにする 2010年4月8日(木))
「相談員が思う非常識は消費者にとって常識である」ということを尊重せずして、あっせんや助言は上手くいきません。
消費者の主張を鵜呑みにするのではなく、「こう考えてもおかしくないな」、という心構えを持ち、相談者を受け入れることが相談者との信頼を築く一歩になります。
私たちができることは、スタンダードを示して、消費者の常識を非常識に変えていくという「説得」が必要です。
「説得」とは相手の考えを否定することであり、並大抵の努力では納得してもらえません。
相談員が常識的な考えを説明すれば簡単に理解してもらえると軽く考えると、相手を否定し反発されます。
たとえば、「お店に出向いて買った商品を気に入らないから返品を申し出たら断られた。おかしいのではないか。クーリングオフできるのではないか。」という相談が少なからずあると思います。
私たちは、「当然返品はできないし、返品は自主交渉で、返品や交換はお店のサービスである」という常識を持って相談者に説明しますが、これを、さも当たり前のように説明すると相談者は怒り出します。
消費者教育が十分でない社会では常識力の欠如が存在しています。
それゆえ、相談者の常識を否定し、人格をも否定することにつながるからです。
これをクリアするために「説得」というスキルが存在し、説得のコミュニケーションが必要になってくるのです。
そこで今一度考えて欲しいのは、あなたの常識は本当にスタンダードな常識ですか?
相談者だけでなく、他の相談員や職員や事業者と話をするに当たって、その常識が常識であると十分確認できているでしょうか?
相談員の常識が実は常識ではなかった場合、相談員の常識を否定されることは、先に述べたことと同じ現象になり、相談員の人格を否定することになります。
しかし、大事なことは、反発せず、素直にきける柔軟性があるかどうかです。
説得されるのではなく、気づきをもって自主的に自分の常識を修正してほしいと思います。
自分の常識が常識ではないと指摘してくれる人は貴重な存在です。
大切にしてください。