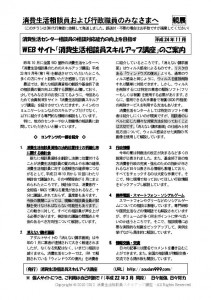できる方法を3つ考える(おすすめブログより)
「草野健次ブログ」より引用しました。
http://kenjikun.exblog.jp/
過去には、2011年6月25日・2012年10月29日の記事で紹介しました。
第1667話・・・最初はわからなかったがあ~、そういう意味だったのか・・・
https://soudanskill.com/20110627/230.html
第1863話・・・気をつけたいこと
https://soudanskill.com/20120710/477.html
今回は
第1928話・・・できる方法を3つ考える
http://kenjikun.exblog.jp/18615165/
2012年 10月 29日
ポジティブシンキングが重要です。
このサイトのフレーズ「日々勉強、日々努力」
まずは自分自身への呼びかけです。
そして、周りへの呼びかけです。
以前にも書いたことがありますが、相談者の要望に対して、「できない」ことであっても、すぐに「できない」というのではなく、「できる」ことを何とかして探してあげましょう。小さいことでもかまいません。道筋を示してあげましょう。必死の思いで勇気を振り絞って消費者センターに相談したんです。
相手の立場・相手の気持ちを想いやると、自然とできる行動です。