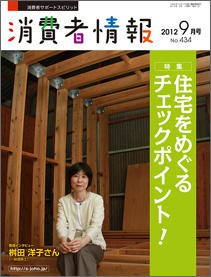消費者情報 2012年9月号 (関西消費者協会)
今月号から気になる記事を紹介します。
①特集「住宅をめぐるチェックポイント」
・マイホーム選びと購入時のチェックポイント窶・I
→中古住宅の「瑕疵担保責任」は、売主が個人の場合は全部免責特約をつけることも可能だが、部位を限定して3ヶ月間だけ責任を負う特約をつけることが多い。売主が宅建業者(不動産業者)の場合は部位を限定したり、責任期間を2年未満とする特約をつけることはできない。2年としているのが通常。
※細かく見ると知らないことばかりでしたので勉強になりました。自分の家を売ったときに不動産業者にいわれて3ヶ月の部位の特約をつけ、3ヶ月経過するまでどきどきしていましたし、家族が家を売ったときに浴室の配管を特約で直すことになってしまったり、実際に経験していました。
・賃貸住宅の契約から退去時までのチェックポイント!
→契約時、入居時、退去時のチェックポイントが、まさに相談事例で出てきそうなことに関して法律やガイドラインで詳しく解説されています。これは手元においておくと相談業務の役に立ちそうです。
・知っておきたい住宅の関連法規
※住宅の関連法規がまとめられているので、いざというとき、どんな法律を参考にすればいいのかが分かりやすいです。
・相談スキルアップ窶・I住宅関連トラブルに関する聞き取りとあっせん
※住宅に関する相談対応の概略がまとめられていますが、ボリュームが少なく消化不良です。
②判例に学ぶ
「震度5」は地震免責条項における「地震」か?
・東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。
③多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
熊本県阿蘇地域の消費生活センターでは、多重債務問題の取り組みとして行政間の連携がうまくいっている現状について詳しく書かれています。消費生活センターによっては多重債務への取り組みの範囲がさまざまですが、一つの参考になります。
④ネット漂流 Vol.4 「コンプガチャ規制の波紋」
・ソーシャルゲームは、はまってしまうと抜けられない。
・無料ゲームサイトでどのようにすれば無料で遊び続けられるかというと、お金を払ってくれるリーダーのもとで遊べばいい。
・おだてられたリーダーは、長時間利用し短期間に課金してしまう。
・未成年者がリーダーになってしまうこともある。
・コンプガチャ規制によりビジネスモデルの変化がおき始めている。
※ソーシャルゲームを知るにはソーシャルゲームをやってみることです。研修でゲームの仕組みの話を聞いていてもリアルな場では理解できないし、相談者の気持ちに寄り添うこともできないと思います。
リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年9月号