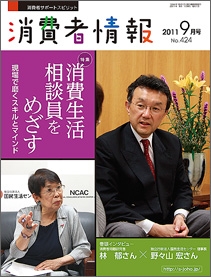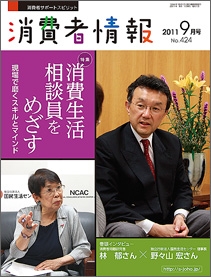いろんな意味で9月号は注目です
①巻頭インタビュー
「あるべき消費生活相談員増を語る」
・消費者被害は、なぜなくならないのか。消費生活相談はどうあるべきなのか。消費生活相談員のマインドを語る。
・国民生活センター理事長とのインタビュー
※あいかわらず、というところです。残念ながら、現実にぶつかってきた問題の根っ子に目を向けない限り同じですね。
②特集 消費生活相談員をめざす 現場で磨くスキルとマインド
「消費生活相談員をめざす」ためのスキルと心構え(東京経済大学教授・弁護士 村千鶴子)
・相談業務を行う上での基礎的なスキルである「聞き取り」「説明と説得スキル」の重要性について
・3つの聞き取るスキル・・・相談者の話を十分に聞く、相談者の話を整理しつつ聞く、相談員が適切な助言をするためにさらにきめ細かく不足している情報などを聞き取る
・説明スキル・・・事業者にはわかりやすく説得力のある説明、消費者にはどう説明すればわかってもらえるか
・法律スキル・・・何も知らない人に説明するためには本当によく理解している必要がある。
消費生活相談員の現状と課題(日本女子大学教授 細川幸一)
・消費生活相談員のおかれている環境や処遇について、消費生活センターの歴史的背景から、ボランティア+多少の報酬という形で相談員を確保し、行政職員は行わない体制となった。
相談員の地位とその展望(弁護士 国府泰道)
・消費生活相談員の勤務状況の現状、相談員の待遇改善の方策、相談員の雇い止め撤廃の方策
相談スキルは現場で磨かれる!(関西消費者協会相談グループ 白﨑夕起子)
・初めて相談に携わる相談員に向けた、実務の基本的な心がけについてのベテラン相談員からアドバイスです
※経験をつめばつむほど、「検証をする」「先輩相談員から学ぶ」はずなのに、実は大きなギャップとなるかもしれないということも分かってくるでしょう(検証をせず同じ失敗を繰り返すがやはり検証をしない、先輩相談員が必ずしもプラスになるとは限らない)。
消費者行政関連年表 窶披蘀50年のあゆみ(編集部)
※「消費者行政に関するできごと・法律」と「消費者問題・社会のできごと」について50年分がまとめられており、非常に勉強になります。
相談員の素顔に迫る窶・I ほかで言えない本音トーク(編集部)
・5人の現役相談員から、相談員になった動機、苦労や悩み、やりがいと生きがい、仕事の不満あるいは問題点、について生の声を聞いたものです。
・コメントしたいところがありますが、めておきます。
報告!「これがクレーマーの実態です」(編集部)
・初動における言葉づかいや態度がまずいと「火に油」を注ぐことになるのは言うまでもない。
・相談業務につきものと思えば、そのこともこの仕事の面白さの一つ。
・絶対に自分が正しい、という立場を押し通すクレーマーを相手にするのは相当のエネルギーを必要とする。何が言いたいのか、何をどうしたいのか、何が不満なのかをキャッチしなければいけない。
・憤りには私憤と公憤がある。
・相談員のおざなりな態度、丁寧な聞き取りもせず、予想通りの処理方法しか言わない態度に憤りの理由がある。
③現場からの情報 【相談】 海外旅行で請求された高額なスマートフォン利用代金
※海外でも気軽に所有の携帯電話を使用する、そこまでして携帯電話を使いたいのかと思ってしまうのは、時代遅れの証拠なのでしょうかね。「消費者の権利」として説明不足を追及するのも大切ですが、なんでも他人任せにするのではなく、自分で説明書を読み調べるなど、自分の行動がどうなるのかということを知っておく「自立した消費者」になるべきだと思います。
④温故知新で読み解く 消費者問題 「にせ牛缶」事件
消費者問題での歴史では重要事件です。これをきかっけとして、景表法の制定、食品衛生法の改正につながりました。今一度、事件を振り返ることができるとともに、事件が明るみにいなったきっかけとしえt現場の担当者のひらめきが寄与していることも書かれています。
⑤判例に学ぶ
「金貨金融」について公序良俗に反し契約全体が無効であるとした事例
札幌簡易裁判所平成23年1月14日判決
・実質上は金銭消費貸借契約で、年利率2000%弱の割合の高額な利息は暴利契約に該るとして、売買契約(実質上は金銭消費貸借契約)は公序良俗に反し無効である、とした。
③団体訴権への展開 消費者支援機構関西(KC’s)
更新料条項についての最高裁判決と消費者契約法
リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年9月号