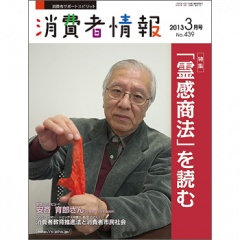消費者情報 2013年3月号 (関西消費者協会)
今月号から気になる記事を紹介します。
①特集「霊感商法」を読む
・「霊感商法」事案の特色と対策
→霊感商法の歴史的経緯と問題点を明らかにし、その法的救済手段について解説する。
・信教の自由と違法性のカラクリ 統一教会による霊感商法
→統一教会によって大金を奪われ人生を破壊された人は数知れない。宗教活動に名を借りて行われてきた「霊感商法」の全体像を探る。
・「霊感・開運商法・占い被害110番」から見た消費者被害の現状と対策
→霊感・開運商法における消費者被害の典型的事案を紹介し、規制状況とその対策について報告する。
・開運商法の事例と対策
→開運ブレスレットの購入をきっかけに次々と開運商品を売りつける手口に注意窶・I
・「占いサイト」と子どもたちの危険な関係(IT情報技術推進ネットワーク代表 篠原嘉一)
→子どもたちの心に忍び寄る「占いサイト」の裏側では、親の知らない怖い世界が展開している。
いともカンタンに個人情報が手に入る、満たされない心と占い、「神待ち」という魔手
・悪徳商法に通底するマインドコントロールの恐ろしさ
・相談スキルアップ窶・I霊感商法トラブルに関する聞き取りとあっせん
※開運グッズが新聞や新聞広告、雑誌にあふれています。「お守り」レベルの考え方だったら許容範囲ですが、今回特集されている次々商法や宗教に身をささげるレベルにまでなると問題です。ネットの普及や手口の巧妙化により、その境界線が判断できないような事例が増えています。
②判例に学ぶ
「動機の錯誤による連帯保証契約の無効を認めた事例」平成24年5月24日東京地裁判決
・兄のビルの融資の連帯保証契約をする際に、ビルの資産価値を過大に説明し、債務が払えなくてもビルを売却すれば連帯保証人に請求は来ないとして銀行と契約をした。兄が履行できなくなったが、ビルの資産価値は当初から低く、連帯保証人に保証債務の履行を迫られた。
→銀行の説明により、保証人になったのは、銀行の説明により請求がこないと考えて契約したので、この契約の動機となった銀行の説明が誤認(不実告知・不利益事実の不告知)に当たるとして、「表示された動機に錯誤があったから要素の錯誤により無効である」と判断した。
※民法の錯誤無効を勉強する場合の「要素の錯誤」と「動機の錯誤」の違いについて勉強になるので、ぜひじっくり読んでみてください。
③現場からの情報 【相談】通販サイトの有料会員窶蘀!?
・通販サイトで書籍を購入した際にクレジットカードの明細に覚えのない会費の請求がされていた。
・確認したところ1回につき500円かかる当日配送サービスが無料で何でも受けることができる会員制度があり、その年会費が3900円だった。
・相談者に確認したところ、購入時に当日無料配送を利用したとのことだったが、有料との表示はなかったとのこと。
・キャンセルをしなければ1ヵ月後には有料会員になるとの説明が申し込み画面とは別のヘルプにあったり分かりにくい表示だった。
・これらを指摘したところ返金された。
※いわゆる最初の1ヶ月が無料になる「お試し会員」のことですね。キャンセルしなければ有料会員に移行してしまうので、レンタルDVDのネット会員サービスでもよくあります。今回のような問題のある業者は別として、ごくごく自然にこのような会員方式が存在しますので、同種の相談があった場合は、どのような制度になっているのか、解約方法などの説明表示は分かりやすいかを確認する必要があります。
④ネット漂流 Vol.9 「『LINE』で荒れる子どもたち」
・最近、「LINE]を起因とするトラブルの相談が学校現場で急増している。
・ラインは何より手軽に利用開始できることで会員を確保している。
・ラインをダウンロードする際に「電話帳のデータを利用する」を承諾すると、登録している電話番号がライン側に送られ、相手がラインを利用した時点で紐づくため、昔付き合っていた元彼まで再びつながりを持ってしまう。おまけにこの繋がりは切れない。
・ラインが起因して校内でのゴタゴタが増えているのはこのためだ。電話帳という限られた範囲の中で繋がり合う為小さな範囲でトラブルがおきているのだ。
※通勤電車で見かける女子学生はみんなラインをやってますね。私はやっていないので分からないことが多いのですが、ネットのサービスは初期設定で個人情報をばらまくような設定になっていることがあるので、設定変更するなど注意が必要です。この初期設定というのはフリーミアムならではの商法ですね。
リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2013年3月号