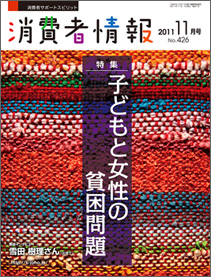消費者情報 2011年11月号 (関西消費者協会)
①特集 子どもと女性の貧困問題
特集1 拡大する貧困と生活保護の動向 貧困の連鎖から希望の連鎖へ
特集2 女は貧乏に生まれない 女を生きて貧乏になるのだ長く生きれば生きるほど
特集3 教育現場から見た「子どもの貧困」
特集4 母子家庭の仕事と暮らし 貧困と偏見のなかで
特集5 不平等社会と消費者問題
特集6 いま求められる社会的包摂の精神 震災復興と貧困の現場
特集7 「社会保障・税一体改革成案」で国民生活はどうなる?
特集8 社会保障制度関連年表窶披鐀 50年のあゆみ
・貧困問題の中でも子どもと女性にターゲットを絞った特集です。切実な内容です。現実を良く知ることが出来ます。
※貧困問題は消費者問題の枠を超えて社会問題となっています。正直言ってコメントしにくいです。問題が単なる金銭的なものであるばかりでなく、離婚や虐待やDVなど人間性に関わってくるものが根底になっているからです。予算措置は切っても切れないものです。一方、それは税金から支出されるものです。今の借金まみれの日本でそう簡単に予算措置はかないません。増税が必要と分かっていても、社会全体は増税には消極的です。日本の国自体も貧困問題を抱えています。本気になって社会全体で弱者を支えるという機運が生まれればいいのですが、昭和40年ごろの高度成長期と違い、人間関係がぎすぎすしています。思いやりの心が失われています。そんな中で、相談員は行政に存在し、行政的なルートで救済する道を助言してあげることができます。消費者センターの管轄ではない場合もありますが、やっとつかんでくれたわらを切ることなく、少なくともパイプ役としての役割を果たすべきだと思います。
※私の学生時代の友人もDVで離婚しましたが、十分な慰謝料も養育費ももらえず、子どもも精神的な問題を抱え苦しんでいます。私の紹介で結婚したようなものなので責任を感じます。とにかく、弁護士に相談して、裁判をしてでも金銭的なけじめをつけるように助言しています。
②判例に学ぶ
「順位式方式」による預貯金債権の差押の申立を違法とした最高裁決定
最高裁平成23年9月20日判決
・最初に判決と強制執行の一般論について解説しています。
・裁判で勝訴し、相手方が賠償金を支払わない場合は強制執行ができます。しかし、悪質業者の資産の状況は分からず判決も無視します。被害者に勝訴判決が出たにもかかわらず被害回復ができない仕組みになってしまっています。
・被害金を銀行から差し押さえるために「順位式方式」というのがあり、下級裁判例では認められてきたのに、今回の最高裁判決で違法とされました。被害者救済や法秩序維持の視点は全くないと批判しています。
※「順位式方式」というのを始めて聞きました。悪質業者は徹底的に厳罰に下すべきだと思います。しかし、現実と理想にギャップがあり、地団駄を踏むばかりです。
最高裁HPの判例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf
リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年11月号