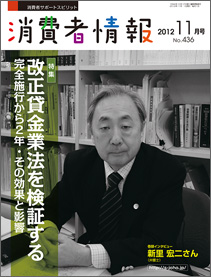消費者情報 2012年11月号 (関西消費者協会)
今月号から気になる記事を紹介します。
①特集 改正貸金業法を検証する
・インタビュー「改正貸金業法」完全施行2年を振り返る
・データで見る改正後の貸金業界の動向と現状
・「改正貸金業法」完全施行から2年の現状と課題
・経済弱者層に浸潤するヤミ金融 過度な規制の見直しを
・相談現場からの報告
「おせっかい」精神が市民を救う 多重債務者の発見と支援の仕組みづくり
多重債務問題に軸足を据えて
・消費者委員会(第98回)「改正貸金業法」概要報告
・多重債務問題、法的解決への道筋 債務整理の4つの解決手段
→自己破産・免責、個人再生、特定調停、任意整理についての解説です
・相談スキルアップ窶・I多重債務問題に関する聞き取りのポイント
→センターによっては多重債務相談を受けるかどうか、どこまで受けるかが異なりますが、対応すべき内容が分かりやすくまとめられています。ほかの相談でも同じですが、借金を少なく申告する相談者の場合解決が頓挫することがあるので、ありのままを話してもらうために信頼を得る対応が必要だというのは同感です。
※改正貸金業法が正しかったのかどうか、様々に議論されています。確かに、大手サラ金が倒産したり、銀行系列に吸収されたり、過払い金問題が継続中であったり、短期のつなぎ融資ができなくなったり、貧困ビジネスが問題になったり、立場立場で意見が異なるのは仕方がありませんね。貸し金が必要だという声があっても、歴史を見ていくと、大きな波に飲まれるのはどこでも同じだと思います。ちなみに、日本消費者金融協会の業界誌の「クレジットエイジ」12月号では「貸金業法改正に見る政治の失敗」として特集が組まれています。
②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
地方における多重債務問題に対する活動報告
・岡山県真庭市は弁護士がいなかったが、弁護士会等の支援により巧拙事務所が設置され、弁護士1人が勤務することになった。
・地方特有の多重債務問題がある
・債権者が債権回収の相談にきた場合、利益相反により多重債務者の相談・依頼を受けることができなくなる。狭い地域に弁護士が1人しかいないという限界を感じる。
③現場からの情報 【相談】 元本割れリスクのある外貨預金
元本割れリスクのある外貨預金
※これはひどい商品ですね。結局、契約書に書いてあれば、勧誘時の言った言わないの話は無効にされてしまうのが問題ですね。
④現場からの情報 【製品事故】 製品事故を未然に防ぐ
・安全確保の3要素・・・人間・製品・使用環境
・OKAトライアングル(安全性確保の概念図)
・製品での安全確保・・「本質安全設計/防護装置/警告・注意表示」の③ステップ
・技術基準や規格についての考え方
・「ルールベース」から「知識ベース」へ社内基準の考え方
・安全対策上の8つの障害
・まとめ(課題と方向性)
※技術職員や商品テスト担当者のいないセンターでは製品事故の対応が難しい場合もありますが、今回の記事は製品事故・製品安全の基本的な考え方をNITEが解説しています。少し難しい書き方をしているところもありますが、ぜひ読んでください。
⑤判例に学ぶ
「消費者金融の不動産担保ローンへの「切替」について充当計算を否定した最高裁判決」最高裁平成24年9月11日判決
・無担保ローンを「おまとめローン」として不動産ローンを契約し複数の借り入れを精算し一本化した。
・無担保ローンには過払い金があり、実は借り換え時に完済できていたことが分かったが、おまとめ時にそれを充当すべきとの主張に対して、別個の契約として、この二つの取引が一連のものであるということを否定した。
・無担保ローンがリボ払いで貸付と弁済が繰り返されるのに対して、不動産ローンは元利金等弁済であり、別個の契約となり、無担保ローンの過払い金は時効である。
※いつもの判例開設に比べて難しい法律解釈が少ないので読みやすいです。
最高裁判例を抜粋しておきます。
裁判所トップページ > 裁判例情報
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82533&hanreiKbn=02
⑥団体訴権への展開
「国民生活センターの国への意向に引き続き注視を」
※「国民センターの国への移行」「国民生活センターの新たな位置付け」について簡潔にまとめられています。
私は言うほど興味は持っていません。どちらに転がっても、結果は見えているからです。今までとたいして変わらない様な気がします。唯一、国民生活センターが直接(間接的でも)有効的な行政指導をしてもらいたいという希望はあります。とはいえ、結局は国と現場との距離や考え方は遠く現場で自分たちでがんばらなければならないと思います。。
⑦暮らしと経済「あなたの思考は指数型? 双曲型?」
・「あなたは今の1万円と1年後の1万円のどちらを取るか?」
・今の1万円は現実のもので、将来の1万円は不確かで1年待たねばならないので、今の1万円よりも劣る。これがお金に利子がつく理由の一つとなっている。
※経済の基本的な話で改めて読むと勉強になります。今回は貸金業法を例に考察されていますが、私は真っ先に「オプション取引のプレミアム」が頭に浮かびました。
⑧ネット漂流 Vol.6 「炎上する“ネットいじめ”の裏側」
・いじめ問題がネットで取り上げられると新聞とは少し違うものとなる。
・ネットでは誰もが書き込みできるため、炎上することがある。
・炎上して盛り上がると、そのサイトへのアクセス数が増えて、広告収入で利益を得ることができる。
・利益を得るために意図的にあおることもある。
・ネットでは、いつまでも書き込みは残り消えることがない。
・面白半分であげた動画もひとり歩きしてしまう。
・子どもたちはお金のために動く大人に利用されている。
※ブログやツイッターなどで気軽に情報を発信できる時代になりました。何気なく発信した情報が社会的に問題になったとき、2ちゃんねるなどで本人を特定する行動が連鎖的に発生し、糾弾される。本人は再起できないぐらいに叩きのめされる。まさに、「ネットいじめ」です。情報発信する側はそのことを十分に理解しなければならないと思います。
リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年11月号