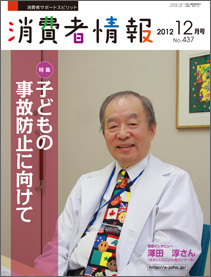携帯3社の価格戦略 その1 ソフトバンク
前回のつづきです
携帯電話・スマートフォンのお得な買い方 (本体価格の季節変動) 2012年11月28日(水)
携帯3社といえば、ドコモ、au、ソフトバンクです。
この3社の本体価格の戦略は特徴的であり、各社の方針がよく分かりました。
大まかに今までの歴史と現在と今後の展望を書いてみます。
まず、携帯電話の本体や基本料金に価格破壊を行い、プライスリーダーとなったのがソフトバンクです。
BBフォンやADSLの0円ばら撒き戦略と同様、赤字でもいいので消費者の初期投資を無料に近い激安にして、顧客を獲得します。
ほかの2社は全く無視というスタンスでした(それが後にあだとなりました)。
顧客さえ獲得してしまえばこっちのものという考え方です。
当時は回線品質の劣勢を価格戦略でカバーしていました。
0円携帯は当然として、キャッシュバック、基本料一定期間無料などあらゆる手段を講じます。
他社がまねできない戦略をして赤字でも顧客獲得という考えです。
ゴールドプランで0円を強調したあまり、景品表示法違反に問われたこともありました。
当時は消費者センターに苦情が寄せられまくりというところでしょうか。
最初に本体価格分割払いで、同額を毎月割引し、実質0円にする手法もソフトバンクが始まりですし、基本料金の無料期間を設定したのもソフトバンクが最初でした。
8円携帯という歴史を作ったのもソフトバンクです。
8円携帯は別途解説しますが、本体価格0円、毎月の維持費が8円(ユニバーサル料金のみ)で携帯電話を持てるというものです(今はできません)。
そして、iphoneで一気にシェアを伸ばしました。
2年ほど前までは、1つ前のモデルであれば0円携帯もありました。また、「スーパーボーナス一括0円」という合言葉もあります。
そのころは高機能携帯で各社が競い合っている時代です。
メーカーが同じで基本的な性能も同じでキャリアが別という高機能携帯の価格面でのソフトバンクの特徴は、本体価格がほかのキャリアと違って高かったことです。ほかの2社が一括払いで5万円ほどの定価であったところをソフトバンクは8万円ほどの設定でした。
しかし、毎月の割引額を設定することで、安く見せかけていましたが、実は他社とあまり変わらないという罠も感じました。
その戦略が現在も引き継がれて将来的にも変わらないと思います。
キャッシュバックや商品券などの販売促進費を消費者にばら撒く戦略も2年ほど前までは、かなりあからさまにばら撒かれていましたが、現在では5000円がせいぜいで以前のようななりふり構わぬばらまきはなくなったように感じます。
おそらく、ある程度の顧客の囲い込みに成功したからでしょう。
今のソフトバンクは、iphone(ipad)一色というところですね。
最新モデルが出ると、おいしい条件を提示して、既存のiphone(ipad)顧客に買い替えを勧めます。
auとのiphone戦争にも結局は勝っているようです。
最新端末は基本的に定価販売になるので、本体価格競争の消耗戦にはなりにくいです。
逆に前のモデルはお買い得になります。
iphone(ipad)でかなりの利益を獲得していますが、ほかのスマートフォンや携帯電話にはあまり力を入れていないように感じます。
力を入れていないので、特に値下げ競争する必要もないのです。
高機能携帯は安くなりませんが、簡単携帯は安いです。1万円程度で買うことができます。
注意:この記事は私の全く個人的な見解です。勝手な推測を多く含んでいます。当然地域による違いもあると思います。あくまでも参考ということでご了解ください。そして、実際に店舗を回ってみて、自分の目で確認し感じることが重要と思います。