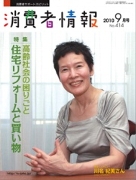解説 ドロップシッピング その4
②ドロップシッピングには(商材として)何が必要か (その1)
ドロップシッピングを始めようとすれば当然何かが必要です。
それを自前でそろえるか、そろったものを購入するか、という選択肢があり、後者が、いわゆる「ドロップシッピング商法」の対象になってしまいます。
解説 ドロップシッピング その1 において次のように書きました
『ドロップシッピングに必要なものは何でしょうか。
無料の「サーバー」では「商用利用」を禁止しているところが多いので、まず、「レンタルサーバー」を借りることになります。
そして、ホームページアドレスを表示するために「ドメイン」が必要となります。
当然ながら「独自ドメイン」がおすすめです。
それらを準備できたら、自分のショップをオープンさせるために、ホームページを作ります。
ホームページ作るためには、「ホームページ作成ソフト」や「ショッピングカート」なども必要でしょう。
さらに、商品を入れ替えたりする日々の「HP更新作業」や来訪者を増やすための「SEO対策」も必要になります。』
今回はドロップシッピングに必要なものを解説したいと思います。
(1)サーバー
・自分のショッピングサイトを開設するためにサーバー(ネット上の自分のサイトをおく場所)が必要です。
無料のものから有料のもの、有料でも安価なものから高価なものまでさまざまです。
・ブログを解説することを考えてください。ライブドア、アメーバ、FC2など無料で利用できるブログがたくさんあります。
申し込めば自分のIDをもらえて一定のサーバースペースを使用することができます。
無料の場合は広告が勝手に貼られてしまいます。有料オプションで広告なしにもできます。
最近はアフィリエイトなどのパーツをブログに貼り付けることができる場合もありますが、かなり制限があると思っていただいたほうがいいです。
規約で商用利用を禁止しているのがほとんどです。
・一方、契約しているプロバイダーからHPを開設するサーバースペースが無料で付いてくる場合もあります。
私は「プララ」を使用しているのですが無料でHPを開設していました。
こちらも、商用利用が禁止されていたり、特殊な機能(ショッピングカートなど)が使えなかったりします。
・結局は、有料のレンタルサーバーを利用することになります。
さて、このサーバーの選択がくせものです。本当にピンキリです。
すなわち、大手企業がトラブル時にもサイトがダウンしないように管理したり、セキュリティを万全にしたりしているレンタルサーバーは容量にもよりますが、1ヶ月当たり数万円必要であったりします。
しかし、家族経営など小規模なものであれば、1ヶ月当たり数百円のものもあります。
質と価格の比較ですね。
初めて車を買うのに、カローラにするのかベンツにするのか、という感じです。
私が利用しているサーバーは、ハッスルサーバーという激安サーバーで、初期費用 1,000円 で12ヵ月2,500円(1ヶ月当たり208円)です。1.5GBの容量があります(必要な容量についての解説は省略します)。私は特に不満はありません。ただし、本格的に商用利用するのであれば、ほかのレンタルサーバーを契約して、少なくともあと10倍の費用をかける必要があるとは思います。
ここで重要なことは自分で選択すると選択の幅は大きいのですが、はじめからセットされたパッケージものだと選択の余地はないということです。すなわち、最初からベンツを買わされている可能性もあるということです。決して悪いことではありませんが、最初からは必要ないですよね。
↓こちらがハッスルサーバーです(以下アフィリエイト広告にもなっています)
![]()
次回は「(2)ドメイン」から「(5)HP(ショッピングサイト)の更新作業」までについて解説したいと思います。
(平成22年9月13日 初稿)
Copyright c 2010- 消費生活相談員スキルアップ講座 – All Rights Reserved